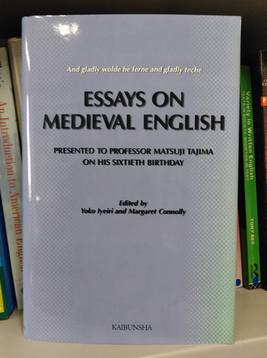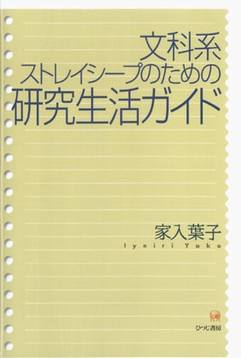言語研究 — 境界を超えるということ
Isabel Moskowich-Spiegel Fandiño & Begoña Crespo García (eds.), New Trends in English Historical Linguistics: An Atlantic View (Universidade da Coruña, 2004)
本書の冒頭に編者による序章として “Old Trends, New Trends” (pp. 17-29)が掲載されている。この中で、通時性と共時性についての以下のように記されている。言語研究における通時性と共時性は半ば前提となっている考え方ではあるが、両者間の境界が必ずしも明確ではない。
“However, there is no clear-cut division in the Saussurean dichotomy synchrony/diachrony. It is undeniable that any synchronic period of a language has a diachronic dimension because it in corporates reminiscences of past stages of that language. Languages are always subject to synchronic variation, hence the existence of idiolects, sociolects, dialects or registers. It is the tension between different variants that provokes language changes. …” (pp. 17-18)
また最近のトレンドとして、分野の境界がこれまで以上に低くなってきていることもある。こちらについても、以下のように記されている。
”Twentieth century linguistics underwent a methodological renewal process which triggered off a widening of objectives and the incorporation of other areas of study (…). All this brought about a new interpretation of historical studies that viewed language as a system characterised by both dynamism and stability at the same time (Tejada Caller, 1999). To explore this paradox the historical linguist has applied different general theories to the study of language evolution: sociolinguistics, cognitivism (…), typology, pragmatics, discourse analysis, corpus lingusitics or grammatlicalization studies”. (p. 24)
本書には、以下の6本の論文が掲載されています。
- ”Syntactic Categories and Syntactic Change: The Development of Subjunctive Periphrases in English” (John Anderson)
- “On Interpreting Old English Data as Evidence for Reconstructing Old English: In Part a Defence of Philology, with Special Reference to Personal Names on Anglo-Saxon Coins” (Colman)
- “Prepositions Referring to Path in Middle English: Bi and Thurh” (Luis Iglesias-Rabade)
- “Use of Progressive Aspect in 18th-Century English: A Study of Personal Letters” (Catherine Smith)
- “Evidence for Diachronic Semantic Change in the Historical Thesaurus of English: A Cognitive Linguistic Approach”. (Louise Sylvester)
- “The Use of the Auxiliary Do in Negation in Tom Jones and Some Other Literary Works of the Contemporary Period” (Yoko Iyeiri)
Iyeiriの論文については、こちらに専用ページも設けています。
家入葉子・堀田隆一(著)『文献学と英語史研究』(開拓社、2022年)
『文献学と英語史研究』の終章である第6章(英語史研究における今後の展望に変えて)では、特に境界を超えるということを意識的に考えてみました。第6章の最初の3つの節は以下のようになっています。
- 境界を意識し、境界を超える(1) — 時代の区分
- 境界を意識し、境界を超える(2) — 分野の区分
- 境界を意識し、境界を超える(3) — 共時性と通時性
本書自体は伝統的な分野の区分と時代の区分に基づいて記述を進めましたが、境界を意識し、境界を超えるという作業と向き合いながらの執筆でした。その気づきを整理したのが終章の前半になります。
本書には、やや詳しい専用ページを設けています。そちらもご覧ください。
大谷直輝(著)『ベーシック英語構文文法』(ひつじ書房、2019年)
『ベーシック英語構文文法』の中に、伝統的な言語研究と構文文法の分野に関する考え方の違いについての記述がありました。伝統文法の中で前提となっている、形態論や統語論といった分野の境界が、構文文法では必ずしも区別されるものではないという点が、以下のようにまとめられています。引用してみたいと思います。
① 形態論 vs 統語論:両者は不可分であり、ともに構文の形式を扱う
② 意味論 vs 語用論:両者は不可分であり、ともに構文の意味を扱う
③ 辞書的意味 vs 百科事典的意味:両者は不可分であり、ともに言語を産出・理解する上で重要である
④ 語彙 vs 文法規則:両者は不可分であり、ともに抽象性や複雑性が異なる文法である
(pp. 207-8)
総合的な観察が求められるようになってきたという近年の研究方法のあり方が、構文文法の興隆をもたらしていると見ることもできるかもしれません。