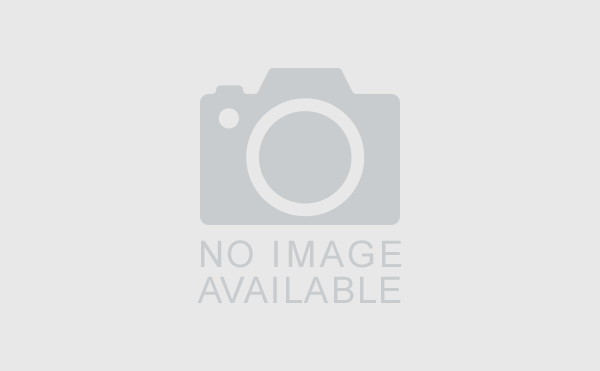『ことばと文字』第18号(日本のローマ字社、くろしお出版、2025年)
語彙と文字の近代化についての特集
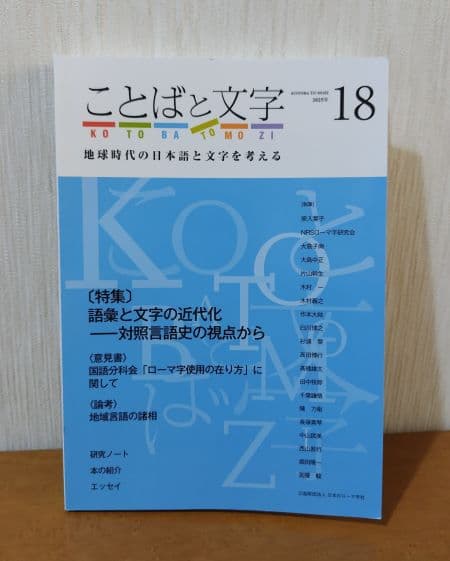
『ことばと文字』第18号で、「語彙と文字の近代化 — 対象言語史の視点から」という特集が組まれました。日本語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語を歴史的な研究方法で探求している著者が、それぞれの立場から「語彙」または「文字」あるいはその両方を取り上げて、寄稿しています。個別の現象やテーマを取り上げるもの、特定の時代を広く扱うものなど、内容は多種多様ですが、言語が違っても共通に議論できる話題が浮かび上がってきた面もあると感じます。
英語の綴り字の収束、特に古い時代における綴り字の変化を取り上げた私の論考は、「15世紀英語の綴り字のバリエーションとその収束―Pepys 2125写本の事例から綴り字研究の課題を考える」というタイトルで、pp. 74-84に掲載されています。15世紀前半のPepys 2025写本の第1テキストにおける綴り字のバリエーションを扱った論考です。
中英語期は綴り字が多種多様であることがわかっていますが、中英語の終わり頃には、バリエーションそのものがなくなるところまでは行きませんが、少しずつその揺れ幅が小さくなっていく現象も観察できます。その揺れ幅の収束のあり方を細かく観察することで、この時代に写本の制作にかかわっていた写字生の言語の実態を読み解くことにつながるのではないかという提案を行うものです。
英語関係では、私のほかに、堀田隆一氏(慶応義塾大)、中山匡美氏(神奈川大)からの寄稿もあります。堀田氏は語彙に焦点をあて、中山氏は私と同じ綴り字ですが、後期近代英語期を取り上げています。英語の綴り字は数百年にわたって模索を続けてきたことがわかります。
他言語と一緒に、広く、しかし一定のテーマをもった議論の場が提供されたこともよい機会になりました。言語史をやっていても、なかなかお隣の言語の歴史までは意識が向かないことが多いなか、視野を広げる機会が与えられたように思います。特に表記にかかわる綴り字は、社会的な要因によって変わってくる場面も多いため、親戚関係にある言語であっても異なる状況が生じてきます。一方で、ある種の規範主義が広がってくるなどの場面では、互いに思潮が影響し合うということもあるかもしれません。対照言語学の面白さは、このあたりにあると感じました。