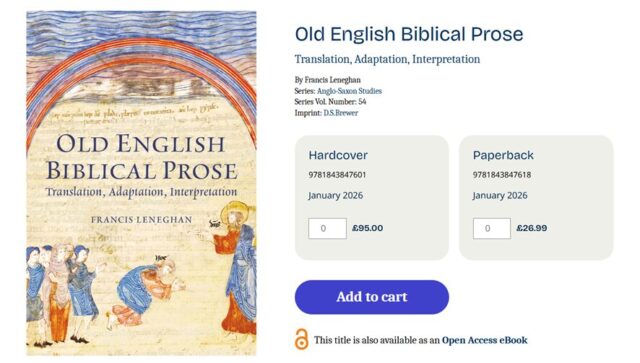『英国の書物出版文化史』(開文社、2025年)
『英国の書物出版文化史 — 著者、出版業者、読者との関係から –』が出版されました。印刷技術がイギリスに導入された1476年から現代にいたるまで、書物がどのような歴史をたどってきたかを専門とする時代が異なる著者がそれぞれに論考を展開し、全体として一つの歴史を紡ぐ形になっています。編者は、この分野で研究を続けてきた都地沙央里氏。
私たちが本を読むときには、その制作の経緯などには注意を払わないことが多々ありますが、本の制作はストーリーが満載だということがわかります。著者と印刷業者の関係、読者との関係、社会との関係などさまざまです。書物にタイトルがついていなかった時代から現代のデジタル時代まで、どのような変遷をたどってきたか、もう一度考え直すのにとても優れた一冊だと思います。
簡単に目次と各章の著者をリストしておきたいと思います。
目次
はじめに
第1章 著者意識と著作権・版権から英国書物出版史を概観する(都地沙央里)
第2章 キャクストン版『アーサー王物語』とためらう奥書題(le morete Darthur)(向井剛)
第3章 シドニーの『アーケイディア』と16世紀散文作品の出版事情(村里好俊)
第4章 人口、識字率、印刷技術 — 『貴公子ハロルドの巡礼』第1、2編重版とコンテクストの変容(山口裕美)
第5章 19世紀の『狐物語』に見る作品受容とテクスト観(都地沙央里)
第6章 『荒地』出版をめぐるメディア文化 — 作者と出版社のマーケティング戦略(池田栄一)
あとがき