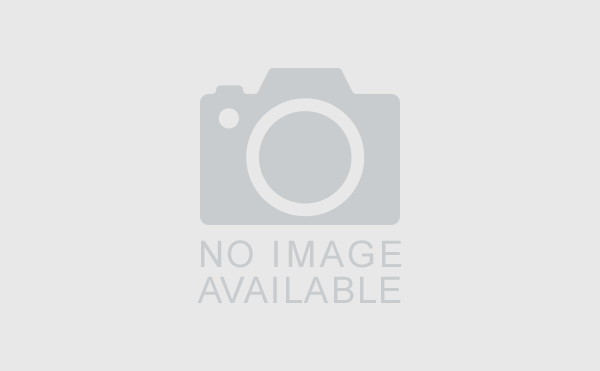構文文法への導き
大谷直輝(著)『ベーシック英語構文文法』(ひつじ書房、2019年)
ひつじ書房のベーシックシリーズから構文文法 (Construction Grammar) についての概説書が出版されました。認知言語学の考え方を多分に含んだとてもわかりやすい構文文法の入門書になっていると思います。入門書とは言いながら、必要な専門書、重要な論文にも多数の言及があります。
近年になって言語分析にしばしば使用されるようになってきた構文文法の考え方は、言語研究をしていると色々な場面で自然に習得している感覚があるのですが、一方で、このような著書により、きれいにまとめて提示してくれることは大変助かります。
構文文法のまとめはとても分かりやすいので、少し長くなりますが、以下に引用してみたいと思います。本文のどの箇所で述べられているかを示す節番号は省略します。
<構文全体について>
① 構文は形式と意味の対からなり、全体がまとまりとして記憶に蓄えられる。
② 構文には、形態素や語のような複雑性や抽象性が低いものから、項構造構文のように、複雑性や抽象性が高いものまでさまざまなタイプが存在する。
③ 構文の形式が異なれば意味が異なる。
④ 構文の形式的な類似性は意味的な類似性を予測する。
<構文の習得について>
⑤ 構文に関する知識は発話の場で繰り返し生じる言語表現から抽出され出現する。
⑥ 構文を習得する前段階として、共同注意フレームを構築する等の社会・認知的な能力の発達を待つ必要がある。
<構文を用いた言語活動について>
⑦ 構文は話者が言語算出や言語理解などの言語活動を行う際の基盤となる。
⑧ 言語の理解が可能であるのは、外部からの言語的なインプットに寄って構文のネットワークの一部が活性化され、意味が頭の中で構築されるからである。
<言語知識としての構文について>
⑨ 構文は構造化されたネットワークをなし話者の言語知識を構成する。
⑩ 構文に関する知識には、構文が使用される頻度、構文が出現しやすい言語使用域、構文の談話的機能や対人機能など、言語使用の場における様々な情報が含まれる。
(pp. 206-207)
文法化と構文文法の関係についてもわかりやすい記述がありますので、引用してみます。
文法化はその名が表す通り、語彙的な要素の文法的な要素への変化を表しますが、構文文法では、文法化をもう少し広く構文化 (constructionalization) の観点から捉えようとします。つまり、文法化をこれまでになかった新しい構文が誕生する過程の一種とみなします。構文化には、内容語が機能語になるものだけでなく、新しい内容語が誕生することもあります。(p. 216)
1990年代以降は、文法化理論が脚光を浴びた時代でしたが、最近は、構文化の方に研究者の関心が少しずつシフトしてきているように感じます。