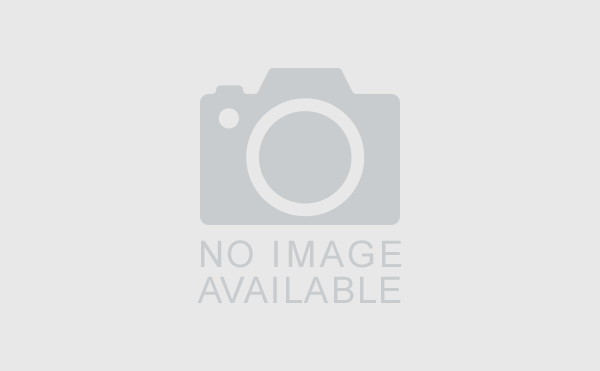身体性 — 舞踊
鈴木晶(著)『踊る世紀』(新書館、1994年)
バレエの歴史についての本です。かなり詳しいこととロシア系の人名などが覚えにくいことがありますので、イタリアからフランス、そしてロシア、それから世界というバレエの歴史の大枠と拠点的な人名を把握した上で読むのがよいかと思います。写真がたくさん掲載されていますし、楽しみながら、しかし読みごたえがある本です。著者の考察もたくさん含まれています。(2022年)
バレエの音楽性と演劇性のせめぎ合いについては、以下のような一節も目に留まりました。引用です。
「サン=レオンがバレエ・ダクションよりもむしろ純粋舞踊を目指したことは、彼が音楽家だったことと関係があるのかもしれない。彼はもともとダンサーであると同時にヴァイオリニストで、時には踊りながらヴァイオリンを弾くこともあった。おまけに作曲もし、バレエ用の曲も書いている。そのために彼はバレエを演劇よりもむしろ音楽に接近させた、と言っていいのかもしれない。」(p. 158)
少し詳しくなりますが、以下に目次を載せておきます。幕仕立てです。
プロローグ
第1幕
第1場 パリのロシア人
第2場 遠い東方の国
第3場 エキゾティスム
第4場 東方の誘惑
第5場 憂鬱症のユダヤ人
第6場 結果と展望
第2幕
第1場 皇帝とバレエ
第2場 ピョートル大帝のアサンブレ
第3場 ディドロ以前・以後
第4場 タリオーニ来る!
第5場 ロシアの舞姫たち
第6場そしてついに、プティパが・・・
第7場 白鳥の湖
第8場 プティパ時代の終焉
第9場 イヴァーノフとゴールスキイ
第3幕
第1場 裸足のイザドラ
第2場 フォーキンの時代
第3場 二人のピエロ
第4場 ペトルーシュカの涙
第5場 興行師の世界
第6場 あの人の生首をください
エピローグ
海野敏(著)『バレエの世界史』(中公新書、2023年)
本書は、副題が「美を追求する舞踊の600年」となっています。日常的にバレエを楽しんでいるバレエ人口は年々増えていると感じる中、こんなに長い歴史があることを踏まえている人はどのぐらいいるでしょうか。
本書は、バレエの歴史をその始まりからわかりやすく解説してくれます。大変長い歴史の中で変容しながら、場所を変えながらバレエが大きく飛躍してきた様子がわかります。バレエというと、いわゆるクラシックバレエをイメージする人が多いと思いますが、バレエには、その前にも、そのあとにも大変面白い歴史があることが分かります。むしろクラシックバレエは、長い歴史の中のほんの一部にすぎないことが分かります。これからバレエがどのように変化していくか、にも思いをはせることができるでしょう。バレエを踊る人にも、鑑賞する人にもお薦めしたいと思います。
本書についても、各章のタイトルのみリストしてみたいと思います。
序章 バレエとは何か
第1章 都市貴族の余興として芽生えたバッロ — ルネサンス期イタリア
第2章 フランス宮廷の祝典から誕生したバレエ — ヴァロワ朝フランス
第3章 宮廷の儀式・儀礼から劇場芸術へ — ブルボン朝フランス
第4章 オペラと一体化したバレエの流行 — ロココ期フランス
第5章 オペラからの独立と演劇的改革 — 啓蒙思想期のヨーロッパ
第6章 ロマンティック・バレエの興隆 — 産業革命期のヨーロッパ
第7章 クラシック・バレエの確立 — 帝政末期のロシア
第8章 総合芸術となったバレエ — バレエ・リュスの活躍
第9章 二十世紀バレエの飛躍 — 振付家・ダンサー・バレエ団
第10章 バレエ界の最前線 — テクノロジーと社会正義
終章 バレエの美を支えるもの