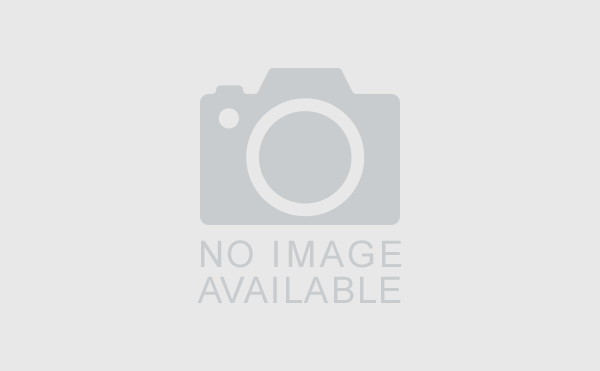英語の語彙
“All people eat and drink”
“All people eat and drink: Does this mean that ‘eat’ and ‘drink’ are universal human concepts?” (by Anna Wierzbicka, 2009)は、語彙の観点から少し面白い論文でしたので、紹介してみます。eat, drinkは基本語彙でどの言語にも存在しているはずだと思っていると必ずしもそうではないことが議論されています。
あまりなじみがないかもしれませんが、KalamやWarlpiriといった言語では、’consume’にあたる単語を使用することでeat, drinkの概念を表すことはできますが、そのメカニズムが異なっていて、あらためてeat, drinkという語の意味の輪郭を考えさせられるとのことです。
eat, drinkは必ずしも普遍的な概念ではなく、ヨーロッパを中心とした見方だと議論されていますが、ヨーロッパの言語以外を母語とする人も陥りやすい落とし穴かもしれません。
一方ですべての語彙について普遍性がないというのもまた誤りで、確かに普遍的な概念も存在することも同時に述べられています。
文献の詳細は、
Wierzbicka, Anna. 2009. “All people eat and drink. Does this mean that ‘eat’ and ‘drink’ are universal concepts?”, in The Linguistics of Eating and Drinking, ed. J. Newman, pp. 65-89. Amsterdam: John Benjamins.
寺澤盾(著)『英単語の世界―多義語と意味変化から見る』(中公新書)
同じく中公新書から出た『英語の歴史』で有名な著者が、今度は英単語の世界に光を当てます。献本をいただき、ありがとうございました。本の紹介をさせていただきます。
本書は英語の語彙の世界を、認知的な視点、歴史的な視点、社会言語学的な視点を交えて解説したお薦めの本です。
目次
第1章 もっとも語義の多い英単語は?
第2章 a hand of bananasはどんな手?
第3章 bottleを飲み干す
第4章 quite a fewはなぜ「たくさん」?
第5章 youは多義語
第6章 トイレを表す語彙の変遷
終章 一語一義主義
Jean Aitchisonの「浴槽効果」についての言及もあります。関連箇所を引用してみます。
「ところで、言い間違いの例では、pinnacleと言うべきところをpineappleと言ってしまったり、anecdotes(逸話)をantidotes(解毒剤)と言い間違えたりするなど、間違えた語は正しい語としばしば語頭・語末が類似しています。オックスフォード大学名誉教授で言語学者のジーン・エイチソン(Jean Aitchison, 1938-)は、人は語の中央部よりも語頭と語末をよく記憶していると考えています。エイチソンは、人が浴槽につかっているとき頭と足の先が出ていることから、こうした言い間違いや語の記憶に関する傾向を「浴槽効果」(bathtub effect)と呼んでいます」(p. 144)
Kate Burridge(著)、Weeds in the Garden of Words: Further Observations on the Tangled History of the English Language
語彙を中心に、英語の新感覚をあつかった著書です。現代的でもあり、一方で歴史的な視点もたくさん含まれています。授業で使用したこともありますが、読み物としても普通に楽しめます。(2017年)